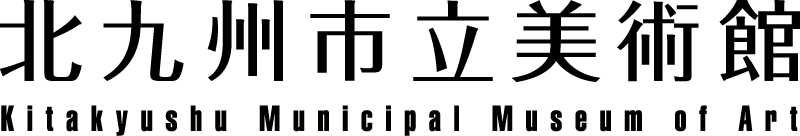概要
美術館のこれまでとこれから
沿 革
北九州市立美術館は、1958年開館の八幡市美術工芸館を前身として、1974年に現在の本館が開館し、これまで、西日本出身作家を中心に、主として近現代の美術作品およそ8,000点を収集・保存し、これらを活用したコレクション展や多彩な企画展を開催して、多くの市民に優れた美術作品に触れる機会を提供してきました。
また、開館当初からの先駆的な美術ボランティア制度や、市内の全小学3年生を対象とした「ミュージアム・ツアー」の実施など、小・中学校と連携した教育普及事業にも力を入れてきました。
1987年には本館に隣接して市民ギャラリーなどを備えたアネックス棟が完成、2003年には市街地の複合施設リバーウォーク北九州内に美術館分館を新設、さらに、2013年にはJR黒崎駅に隣接するコムシティ内に黒崎市民ギャラリーを開設し、それぞれ地域の文化活動の拠点として多くの市民に親しまれています。
また、本館は施設老朽化に伴う大規模改修を行ない、2017年のリニューアル・オープン後は、魅力的な展覧会事業、効果的な教育普及活動、快適な鑑賞空間の提供に取り組んできました。
そして、分館は2023年に開館20周年、本館は2024年には開館50周年を迎えます。これまでの業績を活かし、市民に開かれた、より身近で親しまれる美術館を目指し、さらなる発展に努めていきます。
運営方針の変遷
市立美術館は、開館以来「地方美術館としてユニークな美術作品を収集する」、「市民に密着したリビング・ミュージアムを目指す」という基本方針に基づいて運営してきました。その基本的考え方は、現在でも変わらないものであり、今後も継承すべきものです。
2010年には、基本方針を市民により分かりやすいものにするとともに、地域文化の振興に貢献する市民のための美術館を目指して、あらためて基本理念と基本方針を記した「これからの市立美術館について」を策定しました。さらにこの理念・方針に基づき、翌2011年には当館初の中期計画として「美術館運営5か年計画」を策定し、中長期を見据えた美術館運営の改善に努めてきました。
「これからの市立美術館について」は、具体的取組みに係る事業の終了や美術館を取り巻く環境の変化により、2017年の本館リニューアルを機に内容の一部修正を行なうとともに、名称も「北九州市立美術館の基本理念と基本方針」に改めました。
この修正から5年が経過し、社会や美術館を取り巻く環境はさらに大きく変化しました。本市のSDGsへの積極的な取り組みに基づく多様性・多文化共生の推進や、ポストコロナ社会における美術の価値観、美術館の在り方の問い直しなど、さまざまな角度から考えるべき課題への対応が求められています。
このたび、こうした課題に対応しながら次代を見据える取り組みとして、「北九州市立美術館の基本理念と基本方針」の一部修正を行います。
基本理念
市民の生活に潤いと心の豊かさを創出し、地域とともに成長していく美術館
<基本理念の柱>
1.文化資源を伝承するために
市立美術館は、これまで培ってきた長年の歴史的基盤と成果、そして課題を踏まえつつ、今一度、市民の財産である所蔵作品、活動実績を本市固有の「文化資源」として捉え直すことで、その最大限の活用方法を探り実践していきます。同時に、作品や作家に関する情報を的確に収集、整理するとともに、作品の適切な保存を行い、必要に応じて計画的に修復していきます。
2.作品世界を多様に、存分に味わうために
市立美術館は、美術館を「社会や文化を知るための装置」として捉えることで、美術作品を美術史・美学的な側面からの紹介とともに、社会的・文化的に多岐に渡る視点から分析し、幅広い世代の鑑賞者と共有できる接点を見出します。様々な作品鑑賞の方法を探り積極的に提示していくことで、市民の自由で多様な美術鑑賞を促す努力をしていきます。同時に、学術的な研究に基づいて作品世界を十分に検証するとともに、他分野との積極的なコラボレーションに取り組むことで、美術の多様な文化的意義と多文化共生を探ります。美術を通じて社会や時代、そして自身と向き合う場たりえるような新鮮な環境を提供し、文化的に豊かな生活の一助になることを目指します。
3.地域とともに成長するために
少子高齢化が加速するなか、市立美術館は子どもから高齢者まで幅広い世代の市民を対象に、各人の関心やニーズに合わせた柔軟できめ細やかな対応をとっていくためにも、今後、教育普及活動に対して注力していきます。とくに、作品鑑賞やワークショップ体験を含め、「美術館という場を訪れ、過ごす」という「美術館体験」の演出を重視するとともに、館外活動も積極的に行い、多様なプロジェクトに取り組んでいきます。また、全国初の美術館ボランティア制度を設立したという歴史を踏まえながら、現代社会に適したボランティア組織の再編や事業の見直しを行い、自ら考え行動する自立した組織としてのボランティア活動を支援することで、今後も発展的に継続させていきます。
4.美術の魅力を伝えるために
美術館事業には本来、未来の市民に「何をどのように残していくか」という使命があります。それは美術作品だけではありません。美術館との出合いや作家との出会い、市民間の交流は、かけがえのない一生の思い出となることも少なくありません。その体験を促すためにも、常に生きた情報を現代の市民に発信していくことは、美術館の重要な役割です。
5.魅力的な美術館体験を伝承するために
磯崎新氏設計の市立美術館本館は、1974年に開館しました。現在は、市立美術館分館、黒崎市民ギャラリーも運営し、市内各地で多くの市民に愛され、利用されています。「美術館体験」という出来事が市民の文化的生活を潤し、その感性や感情が周囲や次世代に引き継がれていく伝承自体が、大事な無形文化であり、美術館の存在意義を示すものです。そのためにも、美術館環境と市民の利用機会の場を整備していきます。
基本方針と収集方針
基本方針
地域とともに成長していく美術館「リビング・ミュージアム」を目指します。
開館時に定めた基本方針にある「リビング・ミュージアム」とは、市民生活に密着した「くつろぎの美術館」という意を込めて用いられました。今日ではその要素に加え、市民と美術館が共に活動し育みあう「市民参画の場」としての役割も担っています。そこで、「リビング・ミュージアム」という言葉を、市民とともに「生きる(=リビング)美術館」として捉えなおすことにより、市民とともに成長する躍動的な美術館活動を目指します。
<「リビング・ミュージアム」実現のためのテーマ>
・アートと生きる ~研究・保存機関としての美術館
作品や作家情報などの調査研究を進め、適切に保存します。また、関係者・関係機関との交流を通じて、過去と現在の美術を検証し、その成果を後世に伝えます。
・現代を生きる ~美術を通して時代と文化を考える美術館
時代の変化や文化の多様性をふまえ、美術と社会・生活との接点を探ることで、美術から広がる新たな出会いと発見の場を創出し、発信します。また、現代を見つめ日常を潤すような幅広い美術館事業を実践します。
・地域とともに生きる ~暮らしと共存する美術館
美術館事業を地域コミュニティ活動の一環として捉え、子どもから高齢者まで幅広い世代の市民を対象とした、多様な教育普及事業の充実に努めます。
・最新の情報に生きる ~魅力を届け続ける美術館
さまざまな美術館事業の取り組みを市民や世界に発信します。また、魅力ある巡回展誘致や他館や文化施設との事業連携、広報連携を強化し、美術ファンの生活に潤いを提供します。
・豊かな環境に生きる ~憩いの場としての美術館
美術館体験という非日常のひとときを味わうために、快適な鑑賞空間を維持し、市民の憩いの場としての演出を盛り上げます。
収集方針
開館以来の世界的美術作品を含む収蔵品の蓄積を踏まえ、質の高い優れた美術作品の収集を心がけながら、地方美術館として特色あるコレクションの形成を目指します。収集にあたっては時代背景、作家・作品の関係にも留意します。
開館以来の収集方針や所蔵内容の傾向を踏襲しながら、今後も持続可能な収集活動を目指します。また、作品の保護と修復に努めるとともに、収蔵庫、展示室を含む館内の環境管理に努めます。
<収集方針 3つの柱>
・現代の多様性を示す優れた作品
時代や社会の追体験、考察、共感などを促すような、美術を通じて現代社会とのつながりを示す優れた作品を対象とします。
・地域の美術史を構築する上で欠かせない作品
北九州を中心とした西日本地域の美術史構築のために重要な作品を対象とします。
・近現代美術史の展開をたどる既存コレクションの充実・補完
既存コレクションの体系化を進めるために必要な作品を対象とします。
中期計画に基づく自己評価と外部評価
美術館運営全般に関する取組み
館の運営については、高度な知識や経験をもった専門家、学識経験者等で構成する「北九州市立美術館協議会」において報告し、改善や是正を審議します。あわせて、組織体制の拡充や運営体制の整備に取り組みます。
美術館事業の目標設定と評価
美術館の各事業について5カ年単位で目標を設定し、年次計画に基づき評価・検証します。評価については美術館による自己評価を実施するとともに、北九州市立美術館協議会による外部評価を行います。その評価結果に基づき、PDCAサイクルにより事業の改善とサービスの向上を図ります。